日高敏隆先生がたずさわられた本 3
「変態の生物学」日本発生生物学会編単行本第6集、1978年
(岩波書店、1978.9.20 初版発行、A5判、270p)
|
第1章 無脊椎動物の変態: 竹脇 潔 |
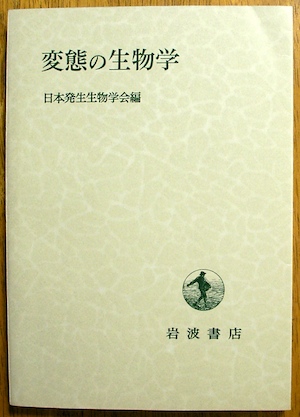
|
『海のプランクトンには数多くの幼生が含まれている。それらは無事に生きていれば、早晩はそれぞれの成体の姿に変態してゆく。陸上の植物の茂みや土の中には、さまざまな昆虫の幼虫がいる。それらは一見しただけでは何の幼虫であるかすらわからないが、それぞれのプログラムに従って変態をとげ、いずれは成虫になってゆく。個体発生の環はそこで完結し、種の維持も保証される。
変態のプログラムは胚発生のそれと同じく、驚くべき精密さで組立てられている。しかし発生生物学は、これまではもっぱら胚発生の諸問題のみに取組んできた。変態はむしろ、実験形態学の対象であった。実験形態学はその後内分泌学の形をとり、内分泌学は生化学をとりこんで大きく発展してきたけれども、それが明らかにしてきたのは、主として昆虫類と両生類の変態にすぎない。
けれど、変態するのはこの2つのグループの動物だけではない。無脊椎動物の大部分についていえば、変態をおこなわないほうがむしろ少数派である。それらの変態の様式はさまざまで、そこにいかなる共通の原則を見たらよいのか、思案にくれるばかりである。
本書ではまず彼らの変態の実体を多くの読者に示してみようと試みた。...(略)
本書の編集に当っては、日高敏隆氏に中心になっていただいた。』(日本発生生物学会編集委員会「まえがき」より引用)
『昆虫の成虫芽についてしか述べなかったけれども、これと同じことは多くの動物の変態についていえるように思われる。ここにみられる二重人格は、とりもなおさず、二つの異なるプログラムの同時的しかも相互依存的な展開にもとづくものである。
変態をしない動物では、プログラムは一つであると考えられる。それはいかにこみいっていようとも、要するに一つの筋の展開をもつ素直なドラマのように進行してゆく。けれど変態をする動物においては、ふつうの意味でいう生存価を異にする二様の形態がプログラムされているために、現象は複雑になっている。幼生は幼生として生きてゆかねばならず、そのための生存価をもつ形態をそなえていなくてはならない。これの方向が成体と同じであるとすれば、幼生は未完成な成体であるということになる。しかし、成体においてはじめて生存価が十分な値に達するとするならば、幼生はそこに到達する過程であるのだから、幼生は生存不能のはずである。変態はこの問題に対する一つの解答であったのではなかろうか。』(日高敏隆「変態とはなにか」より引用)
日高敏隆先生(~2009.11.14)が亡くなられて丸2年がたちましたが、学生時代にお世話になった加藤憲一先生(~2005.3.12)も執筆された本書を思い出しました。日本発生生物学会ができてまだ10年目の年に出された本でした。
(2011.11.14. Yo )
→memory Top